
石破政権の金融/経済政策や少数与党による政局の不安定化、米国トランプ政権の関税政策など、世界を取り巻く情勢は日増しに厳しくなっています。2024年は世界的な選挙イヤーでしたが、日本国内では2025年も都議選や参議院選挙が予定され、引き続き、政治の不安定化が続くことが予測されます。
円安や株価の目減り、米国債の下落等、手元の資産をいかに守り、どのように価値を高めていくか、なかなか判断が下せない時期かもしれません。
そこで今回は、資産保護の新しい選択肢? 「ステーブルコイン」のお話です。そもそもステーブルコインとはなにか? 従来の仮想通貨との違いやメリット・デメリットについて解説していきます。
そもそもステーブルコインとは
一言でいえば、ステーブルコインとは価格が安定するように作られた暗号資産(仮想通貨)のことです。
というのも、ステーブルコインという言葉自体、ステーブル(安定)+ コイン(暗号資産)が由来だからです。
ステーブルコインは法定通貨などと価値を連動させて運用されているため、価格が比較的安定しています。従来の暗号資産(BTC)はボラティリティ(価格変動)が激しかったのに対し、ステーブルコインは1ドル=1コインなど価格がほぼ固定されています。
| 法定通貨担保型 | USDT(テザー) | USDC(USDコイン) |
| 暗号資産担保型 | DAI(Ethereumを担保にする) | |
| アルゴリズム型 | 供給量調整により価格を維持(USTなど) |
上記の3つがステーブルコインの代表的な種類の例です。それぞれがなにかの担保に連動するように設計されているため、急激な価格変動のリスクが抑えられるのが強みです。
仮想通貨(暗号資産)との違い
ボラリティ以外でも、ステーブルコインは従来の暗号資産とは一線を画しています。
まず1つ目が、暗号資産(BTC、ETH)は投機対象/ステーブルコインは決済・保管向けである点です。
暗号資産はボラリティがあるからこそ、購入時と売却時の差額を設けることができます。一方で、ステーブルコインは担保を持つため、そもそも価値の変動がそれほど激しくありません。
そのため、投資や投機目的で使われるというより、インフレや為替リスクにより自国通貨の価値が目減りしている人など決済や保管目当てに使われることが多いです。
また2つ目の違いは、中央管理の有無です。
従来の暗号資産は、ブロックチェーン技術により発行元を持たないのに対し、ステーブルコインは特定の会社など発行元が存在することが多いです。
これにより、ステーブルコインはより安全性が強化される一方で、デメリットを引き起こしうることに繋がります。
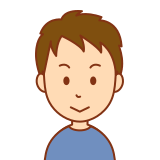
まとめるとステーブルコインは、ボラティリティが小さく投資や投機目的には向いてないけど、それが強みになって「使う」「送る」手段として使いやすいんだね。
ステーブルコインのメリット(魅力)
ボラリティが小さく価格が安定していること以外にも、ステーブルコインの魅力はあります。
国際送金が高速・格安
銀行を仲介して国際送金するには、数日間の日数を要したり、また手数料が高額になりやすいです。一方で、ステーブルコインを使った国際送金は、手数料が数十円から無料と非常に安く、また数秒から数分で送金できる強みがあります。
銀行を介した国際送金では難しい週末/祝日にも、ステーブルコインを使えば、送金が可能になります。
このような特徴により、海外在住者やフリーランス、輸出入ビジネスの人にも便利です。
仮想的な外貨預金として使える
銀行の外貨預金は手数料が高く、利回りも低いデメリットがあります。一方で、ステーブルコインならドル建て資産を自由に・即時に保有・移動できます。また円安などの為替リスクにも強く、通過リスクヘッジにもなります。
DeFi・NFT・Web3サービスの通貨として使える
ステーブルコインは多くのブロックチェーン(Ethereum, Solanaなど)で使うことができます。DeFi(分散型金融)での運用や、NFT購入などで基軸通貨的な存在であり、暗号資産の「安全地帯」としても機能します。
暗号資産には興味はあったけど、ボラティリティや本当に価値あるの?と違和感があった人にも、ステーブルコインは暗号資産のなかでは選びやすい選択肢です。
利回り運用が可能(※リスクあり)
ステーブルコインをDeFiに預けて年利3〜10%程度の利回りを得られるサービスあるそうです。銀行預金よりもはるかに高い利回りですが、スマートコントラクトや流動性リスクには注意が必要です。
ステーブルコインのデメリット
一方で、ステーブルコインにはいくつかのデメリットがあります。
ペッグ(価値固定)が崩れるリスクと発行元への信頼性問題
ステーブルコインのなかには、価格が担保にしているものと乖離する事例がありました。過去にはUSDTやUSTなどの価格が1ドルと乖離したり、「アルゴリズム型ステーブルコイン」は崩壊の事例がありました。また、発行元の準備金の透明性が問題化したり、「本当に1ドル分の資産で裏付けられているのか?」といった懸念がつきまとうでしょう。
規制リスクと税制
各国政府が金融政策の一環として、ステーブルコインに制限をかける可能性を否定できません。また日本国内においては、暗号資産に対する規制が厳しく、税制上も不利になりやすいです。確定申告や税金の納付などステーブルコインを含む暗号資産を保有するには、ハードルになるかもしれません。
そもそも使い道がない
日本国内において、ステーブルコインを使える実店舗はほぼゼロです。また、円安による日本円の実質的な価値が目減りしているとは言いつつも、アルゼンチンなどの一部の国のような極端なインフレが進行し自国通貨が崩壊しているわけでもありません。税務処理上の課題も山積しているため、実用的に使うには、まだまだハードルが高いでしょう。
まとめ:ステーブルコインはこんな人におすすめ
| タイプ | おすすめ理由 |
| 海外送金が多い人 | 手数料/スピードが圧倒的に有利 |
| 暗号資産投資に興味がある人 | 安定通貨としての基軸になる |
| 円安リスクを避けたい人 | ドル建てのデジタル資産として活用可能 |
| DeFiやWeb3を試したい人 | ステーブルコインが事実上の「基礎通貨」 |
| 銀行に信頼がない人(新興国など) | ステーブルコインが生活通貨になる場合も |
まだまだハードルの高い暗号資産とステーブルコイン。政府主導の政策に注目しつつ、興味がある人は始めてみるのも面白い経験になるかもしれません。
また、USDC(Circle社)、USDT(Tether社)、DAI(MakerDAOによる分散型)など、種類によって信頼性や仕組みが異なるため、選ぶ際には発行体や保証の仕組みを確認するのが重要です。

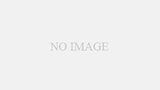
コメント